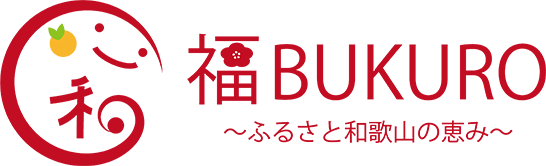日本人が最も愛する日本の伝統的な調味料のひとつに醤油があります。
そして世界ではソイソースと呼ばれて多くの人に指示されています。
日本の食文化のベースとなっている醤油は、今やどの家庭でも食卓に欠かせないものです。
醤油は地域によって味の濃さや甘さなどに特性があり、たまり醤油やうすくち醤油など数多くの種類が存在しています。
そのなかでも和歌山の湯浅町で作られている湯浅醤油をご存じでしょうか?
ここでは和歌山県湯浅町で作られる湯浅醤油について説明します。
Contents
和歌山の湯浅醤油とは

日本に古くからある調味料の醤油、実はその醤油の発祥の地が和歌山県湯浅町であり、そこで作られる醤油こそが醤油の元祖である湯浅醤油なのです。
醤油発祥の地、湯浅町
湯浅町は醤油の発祥地として日本遺産の認定を受けており、醤油醸造業にかかわる建造物や土蔵などが和歌山県唯一の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。
醤油発祥の地として日本遺産を受けた湯浅町には、醤油醸造業に関連する建物や土蔵が多く立ち並んでいます。
湯浅醤油の歴史と伝統

湯浅醤油の誕生は鎌倉時代に伝来した金山寺味噌の製造過程で生まれたものでした。
1254年に紀州由良の禅寺「興国寺」の開祖である「心地覚心」が、中国で怪山寺味噌(現在の金山寺味噌)の製法を学んで日本に伝えたことが始まりです。
金山寺味噌は元々調味料としてではなく食べる味噌として作られていましたが、味噌が成熟する過程で上澄み液が多くしみ出している事に気づきます。
それまで捨てていた上澄み液ですが、ある時それを口にすると芳醇な味であることを知ってから、人々はその上澄み液を調味料として利用するようになりました。
醤油で栄えた和歌山県湯浅町
醤油発祥の地である和歌山県の湯浅町は古くから物流の中心地として栄えており、湯浅の水が良かったこともあって醤油づくりが盛んな町になったのです。
どれだけ醤油作りが盛んであったかというと、江戸時代には湯浅に92軒もの醤油醸造所があったほどです。
【合わせて読みたい記事】
金山寺味噌は和歌山が誇るおかず味噌、その歴史とおすすめの食べ方をご紹介
湯浅醤油の美味しさ
一般的な醤油と比べて湯浅醤油は旨味が濃く、まろやかな口当たりなのが特長です。
その美味しさの秘密は、厳選された国産の材料のみを使用し、約100年使用している大きな吉野杉の木樽で1年半以上の間じっくりと時間を掛けて熟成させていることで美味しい醤油になります。
伝統的な製法を守り続ける湯浅醤油の製造方法

湯浅醤油の美味しさの秘密は、使用している材料へのこだわりと、一流の職人が時間をかけて作る天然醸造にあります。
厳選された材料
湯浅町で醤油づくりが盛んになった理由のひとつとして、湯浅の水が良いことが挙げられます。
そのうえで職人が国産にこだわって厳選した塩、大豆、黒豆、小麦、醤油麹菌などを使用することで伝統の味が守られています。
伝統的な古式醸造法
醤油作りのうえで、大量生産される醤油は大豆を蒸していることが多いですが、時間を掛けて大豆を茹でて作る製法があります。
この大豆を茹でて仕込む製法を古式製法といい、湯浅にはこの製法を今でも守り続けている蔵があります。
古式製法は世界最古の料理書と言われている「斉民要術」(せいみんようじゅつ)に記載されている製法で、その頃からの製法を今も湯浅は伝統として守り続けているのです。
古式製法で作られた大豆は樽入れ作業後から1年半~2年かけて熟成されます。
職人の手による熟練の技
醤油ができるまでのおおまかな作業工程は以下の流れになります。
- 大豆を浸漬させ、小麦を煎り、割砕する
- 大豆、小麦を混ぜたものに種麹をまぜる
- 数日で麹菌が繁殖するので塩水を混ぜてもろみを作り、醸酵させる
- もろみの発酵を進めるために棒で桶の底まで混ざるように撹拌する
- 熟成が終わったもろみを布で濾し、発酵を止めるために加熱する
- あくを取り除いたら完成
これらの工程はすべて職人の手で行われています。
プロの目と経験があるからこそ美味しい湯浅醤油ができあがるのです。
湯浅醤油の種類
昔ならではの製法で作り続けている数少ない醸造元である「湯浅醤油有限会社」、そこで取り扱っている商品だけでも様々な種類の醤油が販売されています。
以下はその一部です。
- 黒豆醤油
- カレー醤油
- だし醤油
- トロ醤油
- 減塩醤油
- たまごかけごはん専用醤油
- 冷奴専用醤油
- ハラール専用醤油
湯浅醤油の美味しい食べ方とは

厳選された素材で丁寧に作られた湯浅醤油は、普段使っている醤油と替えるだけでごちそうに早変わりします。
湯浅醤油をダイレクトに味わうなら刺身や冷奴などにかけて食べるのがお勧めです。
掛けることで素材の持ち味を存分に引き立ててくれますし、卵かけご飯にかければ贅沢な一品に変わります。
じゃがいもやパスタ、あわびなどをバターと一緒に合わせれば旨味が強い濃厚バター醤油味となり、普段食べているバター醤油のワンランク上の味に仕上がります。
丸新本家・湯浅醤油では公式で湯浅醤油を使ったレシピを公開していますので、参考にしてみてください。
また和歌山の漁港で水揚げされた、しらすにもとてもよく合いますので、和歌山にお越しの際には是非試してみてください。
まとめ
日本の家庭の味として母から子へ引き継がれる料理に、醤油は絶対に欠かせない調味料です。
長い歴史の中で多くの湯浅の職人が守り抜いてきた味である湯浅醤油、その歴史と魅力を知れば更に湯浅醤油の味わいを感じることができるでしょう。
和歌山県湯浅町にお越しの際には湯浅醤油グルメやお土産など、是非お召し上がりください。